|
Vol.32 (2008.4.8)
- World Circulation News PLUS
- 2008年度新役員(理事長・理事・監事)が決まりました
- 心肺蘇生法に関するAHA Advisory Statement
|
|
2008年3月29日開催の第72回総会において、2008年度の新役員が選任されました。
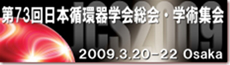
|
◆JCS2009〜第73回日本循環器学会総会・学術集会 公式ホームページはこちら◆
|
| |
[PR記事] |
教えて! 研修医ローテーション表の作り方
あなたの「わからない」に、先輩医師がズバリ答えます |
|
|
|
| |
 |
|
Medical TribuneのMTpro「オーベンネーベン」は、医師同士が匿名で質問と回答を行うQ&Aシステム。日常診療で困っていること、他科の先生に聞きたいことなどやりとりできます。登録・利用無料
ご登録はこちらから → http://mtpro.jp
|
|
1 |
World Circulation News PLUS(Health Day News 提供) |
海外の循環器系ニュースの短報(和訳)をお届けします。(利用規約)
保存期間の経過した輸血液は心臓手術後の死亡率上昇をもたらす
HealthDay News 3月19日
心臓手術において、保存期間が14日を超えた赤血球輸血を受けた患者は、それよりも新しい血液輸血を受けた患者に比べて、術後の合併症発症率や死亡率が高いという研究結果が、「New England Journal of Medicine」3月20日号に掲載された。
米クリーブランド・クリニック(オハイオ州)のColleen Koch氏らは、冠動脈バイパス移植術や心臓弁手術、あるいはその両方の手術中に赤血球輸血を受けた患者において、輸血製剤の保存期間が転帰(outcome)に及ぼす影響について検討した。研究者らは、保存期間が14日以下の“新しい”血液8,802単位の輸血を受けた患者2,872人と、保存期間が14日より長い“古い”血液10,782単位の輸血を受けた患者3,130人のデータを解析した。
その結果、古い血液輸血患者では新しい血液輸血患者に比べて、入院中の死亡率(2.8%対1.7%)、挿管期間の延長(9.7%対5.6%)、腎不全(2.7%対1.6%)、敗血症(4.0%対2.8%)の発症率が有意に高かった。さらに、1年後の死亡率も古い血液輸血患者のほうが高かった(11.0%対7.4%)。
研究者は「心臓手術を受ける患者において、保存期間が2週間より長い赤血球輸血は、短期および長期の生存率の低下とともに、術後合併症リスクの有意な増加をもたらす」と結論付けている。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
パラオキソナーゼ1遺伝子多型が死亡と心血管イベントリスクに影響
HealthDay News 3月18日
パラオキソナーゼ1(PON1)はエステル加水分解酵素の1つで、肝臓で合成され血中では高比重リポ蛋白(HDL)粒子上にアポA-Iと結合して存在し、低比重リポ蛋白(LDL)の酸化を阻害して動脈硬化の進展を抑制するといわれる。このPON1遺伝子の機能的多型性(Q192R)が、死亡や重篤な心血管イベントリスクを高めること、またPON1活性が最も低いグループ(群)では、重症の心血管イベントリスクが有意に高いとする研究結果が、「Journal of the American Medical Association(JAMA)」3月19日号に掲載された。
米クリーブランドクリニック(オハイオ州)のTamali Bhattacharyya氏らは、2002年9月‐2003年11月に同施設で待機的冠動脈血管造影を受けた患者のうち、同意の得られた1,399人のPON1の遺伝子解析を行い、2006年まで追跡調査を行った。その結果、患者の46.3%でQQ192遺伝子型、43.9%でQR192遺伝子型、9.8%でRR192遺伝子型が同定された。
QQ192遺伝子型の患者では、QR192とRR192遺伝子型の患者に比べ、全死亡および重症の心血管イベントのリスクが有意に高かった(調整後のハザード比は2.05および1.48)。また、PON1活性の高さで4分位(quartile)すると、最も高い群(分位)は最も低い群に比べて、重症の有害心血管イベント発現率が有意に低かった(対パラオキソナーゼ7.3% vs. 25.1%、対アリルエステラーゼ7.7% vs. 3.5%)。
著者は「パラオキソナーゼ1は、循環血液中でほとんどがHDL粒子と結合して存在し、HDLの抗炎症作用や抗酸化作用特性を促すといわれている。今回の研究結果は、パラオキソナーゼ1がHDLの作用能を超えた機能的特性を有し、HDLにコレステロール逆輸送能を促進させることにより、HDLのアテローム硬化進展の軽減もしくは抑制作用を導くという概念(コンセプト)をよりサポートするものである」と述べている。
著者の何人かは、製薬企業との経済的関係を報告している。
Abstract
Full Text
新規のバイオマーカーである脂質過酸化物が心血管イベントを予測
HealthDay News 3月18日
酸化ストレスのマーカーである脂質過酸化物(lipid hydroperoxide : LOOH)は、安定性の冠動脈疾患患者において、心血管イベントの独立した予測因子であるとする研究結果が、「Journal of the American College of Cardiology(JAAC)」3月25日号に掲載された。
米エルシダ研究所Elucida Research(マサチューセッツ州ビバリー)のMary Walter氏らは、冠動脈造影で冠動脈疾患を確認した患者634人を対象に、3年間にわたり血清LOOHレベルの測定と心血管イベントに関連する測定値との関連性を検討した。
ベースライン(研究開始時)に最もLOOHレベルの高い4分位(quartiles)に属する患者では、非致死性心血管イベント (ハザード比3.24)および主要冠動脈への介入実施major vascular procedures (同1.80)のリスクが上昇していた。
従来の危険因子と炎症マーカーを調整後、LOOHは非致死性イベントと冠動脈介入実施の独立した危険因子であった。さらに、ベースラインLOOHレベルはチオバルビタール酸反応物質(TBARS)などのLOOHのadvanced products(代謝産物)レベルと相関することが示唆された。Ca拮抗薬アムロジピン服用患者では、プラセボ群に比べて、心血管イベントリスクの低下とLOOHレベルの変化が認められた。
著者は「酸化脂質が、アテローム硬化における明らかな原因的役割が確認されていない状況下で冠動脈疾患のバイオマーカーとされている本領域での研究的バランスを鑑みると、これらデータは、抗酸化療法に対する議論の余地のあることを示唆するものである」と記している。
本研究はファイザー社の資金提供により行われ、また共著者の内2人は同社との経済的結びつきを有する。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
Copyright © 2008 ScoutNews, LLC. All rights reserved.
World Circulation News (WEB)
AHA、ACC、WHO、FDA、CDCの循環器領域関連のニュースヘッドラインを学会ホームページでお届けしています。
2 |
2008年度新役員(理事長・理事・監事)が決まりました |
2008年3月29日開催の第72回総会において、2008年度の新役員が選任されました。詳細はホームページをご覧頂きますようお願いいたします。
2008年度就任役員一覧
3 |
心肺蘇生法に関するAHA Advisory Statement |
一般市民が行うCPRでは、人工呼吸は不要に
ー胸骨圧迫のみのCPR(Hands-Only CPR)を推奨ー
米国時間2008年3月31日午後にAHAより一般市民が行う心肺蘇生法に関する声明が出されました。
Hands-Only (Compression-Only) Cardiopulmonary Resuscitation: A Call to
Action for Bystander Response to Adults Who Experience Out-of-Hospital
Sudden Cardiac Arrest. A Science Advisory for the Public From the American
Heart Association Emergency Cardiovascular Care Committee
Michael R. Sayre, Robert A. Berg, Diana M. Cave, Richard L. Page, Jerald Potts and Roger D. White
Circulation published online Mar 31, 2008
院外での成人の目撃された突然の卒倒に対して、まず救急要請(119番へコール)し、すぐに胸骨圧迫のみのCPRを開始することが勧告されています。
バイスタンダーCPRは、蘇生率を改善するための有効な方法である事はこれまでの研究で示されていましたが、従来のCPR法では人工呼吸が一般市民のCPR施行に対する最も大きな技術的・心理的障壁の一つでもありました。蘇生率を改善するために人工呼吸が蘇生の初期の段階では必ずしも必要ではないことが、昨年日本から発表された2つの大規模臨床研究(SOS-KANTO study group: Lancet. 2007;369:920 -926. 24. Iwami T, et al. Circulation. 2007;116:2900 -2907)を含めた研究で示唆されたことを受けて、AHAは今回の声明を発表しました。今後、AHAでは一般市民向けの心肺蘇生法の講習会ではハンズ・オンリーCPRを指導することになり、これによるバイスタンダーCPR施行率と蘇生率の改善が期待されます。
AHA Emergency Cardiovascular Care ウェブサイト(医療従事者向け)
AHA Hands-Only CPR ウェブサイト(一般市民向け)
JCS Newsletterのバックナンバーをこちらのページでご覧いただけます。
ご意見・ご感想、配信先の変更・中止等は下記のアドレスまでご連絡ください
news-m@j-circ.or.jp
発行:(社)日本循環器学会 http://www.j-circ.or.jp/
本メールに記載された記事を、許可なく転載することを禁じます。
Copyright © The Japanese Circulation Society. All rights reserved.
|



