|
Vol.38 (2008.7.15)
- World Circulation News PLUS
- 「勤務医師賠償責任保険」の更新ならびに新規加入
のご案内
- Circulation Journal 編集委員交代のお知らせ
|
|
「勤務医師賠償責任保険」の募集期間は7月31日までです。期間外のお受け付けはできません。ご注意ください。
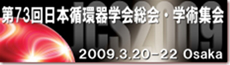
|
◆JCS2009〜第73回日本循環器学会総会・学術集会 公式ホームページはこちら◆
1 |
World Circulation News PLUS(Health Day News 提供) |
海外の循環器系ニュースの短報(和訳)をお届けします。(利用規約)
薬剤溶出ステントとベアメタルステントの転帰を分析
HealthDay News 6月24日
薬剤溶出ステント(DES)は、ベアメタルステント(BMS)使用との比較で、血行再建治療の再施行率を低下させ、死亡やST上昇型心筋梗塞のリスクは増大させていないとの研究論文が、「Journal of the American Medical Association(JAMA)」6月25日号に掲載された。
米、ダートマス・ヒッチコック医療センター(ニューハンプシャー州レバノン)のDavid J. Malenka氏らは、2002年10月から2003年3月の間に、待機的にベアメタルステント留置を受けた38,917人のメディケア加入患者、および2003年9月から12月までの間に待機的にステント留置を受けた28.086人の患者(61.5%は薬剤溶出ステントを使用)について転帰を比較した。
その結果、ベアメタルステント時代の患者に比較し、薬剤溶出ステント時代の患者は、2年間の経皮的冠動脈インターベンション(PCI)再施行率が低く(17.1%対20%)、冠動脈バイパス手術(CABG)の施行率も低かった(2.7%対4.2%)。また、2年間の死亡あるいはST上昇型心筋梗塞の調整ハザード比も同様の成績であった(ハザード比0.96)。
著者らは「他の研究のデータには薬剤溶出ステント使用によりステント血栓症のリスク増大を示唆するものがあるが、我々の研究では対象集団への悪影響は認められなかった」と結論している。また「薬剤溶出ステント使用に関連したステント血栓症のリスクがあるとしても、再狭窄発生リスクおよびその再狭窄に対する治療処置に伴うリスクを低下させるという利益のほうが上回る」とも述べている。
論文著者の2人は、Guidant Endovascular Systems社およびAbbott Vascular社からの研究資金提供を申告している。1人はさらに、ステント技術のベンチャー企業であるTryton Medical社の社長でもある。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
虚血性脳卒中発生から時間経過後のtPA投与の有害機序を解明
HealthDay News 6月23日
組織プラスミノーゲンアクチペータ(tPA)により活性化される蛋白が、脳卒中発症後3時間以上経過した後のtPA投与により出血性合併症(出血性梗塞)をもたらす原因となるとの研究論文が、「Nature Medicine」6月22日号オンライン版に掲載された。
tPAにより血小板由来増殖因子-CC(PDGF-CC)が遊離、活性化されることがすでに示されているが、米ミシガン大学医学部(アナーバー)のEnming J. Su氏らは、このPDGF-CCが血液脳関門の透過性を調節しているかについて検討した。
その結果、虚血がない状態でマウスにtPAまたは活性型PDGF-CCを脳室内投与すると、脳血管の透過性は有意に亢進し、この亢進はPDGF-CCに対する抗体により抑制された。血管透過性亢進は、血管周囲の星状神経膠細胞上にあるPDGF-α受容体を介して生じるが、虚血性脳卒中発症後に抗体でその受容体を遮断すると、発症からの時間経過後のtPA投与によりみられる血管透過性亢進と出血性梗塞がともに抑制されていた。
著者のSu氏らは「これらのデータは、PDGFシグナル伝達が血液脳関門の透過性を調節していることを示しており、脳卒中治療の新しい治療戦略の標的になり得ることを示唆している」と結論している。
Full Text (subscription or payment may be required)
心不全患者対象の2つの研究において進展なし
HealthDay News 6月18日
心房細動とうっ血性心不全のある患者においては、洞調律を維持する心調律コントロール治療によっても、心拍数の管理を行う心拍コントロール治療に比して、心血管疾患に起因する死亡率を低減させることはできず、また抗不整脈薬dronedarone(ドロネダロン)は心不全増悪と関連していたとする2件の研究論文が、「New England Journal of Medicine」6月19日号に掲載された。
1件目はカナダ、モントリオール大学(ケベック州)のDenis Ro氏らの研究で、うっ血性心不全、心房細動既往、および左室駆出率(EF)35%以下の患者1,376人のデータを分析した。対象患者は無作為に、薬剤、電気的除細動、ペースメーカーを用いての洞調律維持か、β遮断薬、ジギタリス、房室結節アブレーション、ペースメーカーを用いての心拍コントロール治療に割り付けられた。患者は平均37カ月追跡されたが、心血管疾患が原因の死亡率は両群間で有意差はなかった。
2件目はデンマーク、コペンハーゲン大学のLars Kober氏らの研究で、症候性心不全と重症左室収縮不全のある患者627人を無作為にdronedarone 400mg 1日2回投与群またはプラセボ投与群に割り付けた。この臨床試験は早期に中止された;中央値2カ月の追跡期間中、実薬治療群でより多くの患者が死亡した(ハザード比2.13)。死亡増加の多くは心不全増悪と関連していた。
Michael E. Cain氏およびAnne B.Curtis氏は同誌の論説で、「心房細動患者において、洞調律維持の好ましさをより明確にするためには、抗不整脈薬治療のもつ低い有効性と高い毒性の関与を取り除いた、心調律コントロール治療戦略に焦点を絞った研究が今後は必要である。アブレーション治療はこの目的にかなっている。従来の抗不整脈薬による治療と比較検討する、心房細動に対するカテーテルアブレーション治療の臨床試験が現在進行中または計画中である」と述べている。
Roy氏および他の多くの共著者は多数の製薬企業との財務関係を申告しており、サノフィ・アベンティス社の協力下に行われたKober氏らの研究でも、数人の共著者が同様の財務関係を申告している。論説の著者らは、特にサノフィ・アベンティス社との財務関係を申告している。
Abstract - Roy
Full Text (subscription or payment may be required)
Abstract - Kober
Full Text (subscription or payment may be required)
Editorial
Copyright © 2008 ScoutNews, LLC. All rights reserved.
World Circulation News (WEB)
AHA、ACC、WHO、FDA、CDCの循環器領域関連のニュースヘッドラインを学会ホームページでお届けしています。
2 |
締切間近です!!!「勤務医師賠償責任保険」の更新ならびに新規加入のご案内 |
団体契約「勤務医師賠償責任保険」の募集期間は7月31日までです。
期間外のお受け付けはできません。ご注意ください。
詳細・お申し込み手続は2008年6月初旬にご送付いたしました書類をご確認ください。
会員の皆様には団体契約による「勤務医師賠償責任保険」に多数ご加入いただいております。
団体契約(保険料割引適用)の更新・新規加入締切は2008年7月31日です。
(保険始期は2008年8月1日)
締切日までにお手続き忘れのないよう、くれぐれもご注意ください。
→ 「勤務医師賠償責任保険」ご案内はこちら
詳細は下記にお問い合わせ下さい
| |
<取扱代理店>
株式会社カイトー
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル
TEL: 03(3369)8811 FAX: 03(3369)3120
E-mail: med.lia-ins@kaito.co.jp
| |
|
|
3 |
Circulation Journal 編集委員交代のお知らせ |
JCS Newsletterのバックナンバーをこちらのページでご覧いただけます。
ご意見・ご感想、配信先の変更・中止等は下記のアドレスまでご連絡ください
news-m@j-circ.or.jp
発行:(社)日本循環器学会 http://www.j-circ.or.jp/
本メールに記載された記事を、許可なく転載することを禁じます。
Copyright © The Japanese Circulation Society. All rights reserved.
|



