|
Vol.41 (2008.8.27)
- World Circulation News PLUS
- 第73回学術集会プレナリーセッション・シンポジウム 演題締切りが迫っています
- 循環器専門医研修施設・研修関連施設 指定および指定更新申請について
- 採択論文のオンラインジャーナル早期掲載のサービス開始について
- Case Reportの取り扱い中止に向けて
|
|
第73回学術集会(大阪)のプレナリーセッション・シンポジウム演題登録締切りが迫っています。
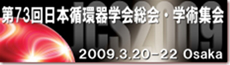
|
◆JCS2009〜第73回日本循環器学会総会・学術集会 公式ホームページはこちら◆
|
| |
[PR記事]
|
|
| |
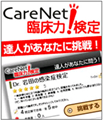
|
|
あなたの臨床の実力
全国で何位?
ケアネット臨床力!検定
受験者数1万8千人突破・無料
詳細はこちらから (提供)ケアネット・ドットコム
|
|
|
1 |
World Circulation News PLUS(Health Day News 提供) |
海外の循環器系ニュースの短報(和訳)をお届けします。(利用規約)
中等度の身体活動が心房細動リスクを低減
HealthDay News 8月5日
軽度ないし中等度の身体活動を行っている高齢成人は、運動を行わない人に比べて心房細動のリスクが低いとの研究論文が、「Circulation: Journal of the American Heart Association」オンライン版8月4日号に掲載された。
米ハーバード大学公衆衛生学部(ボストン)のDariush Mozaffarian氏らは、65歳以上の高齢者で、心房細動に対するモニターと余暇時間および運動習慣に関する情報が得られた5,446人について検討を行った。
その結果、47,280人-年の追跡期間中に1,061例の新規心房細動発症が認められた。余暇時間の活動度と心房細動の発症率に関連性が認められ、これは歩行距離、あるいは歩行速度においても同様であった。心房細動のリスク低減と関連が認められたのは、高度の運動強度ではなく、中等度の運動強度であった。
著者らは「我々の知見からは、中等度の運動により心房細動リスクが有意に低下すること、高齢者における新規心房細動発症例の1/4は、余暇時間での中等度の活動、および定期的な中等度の歩行距離や速度でのウォーキングの欠如に起因することが示唆される」と述べるとともに、「このような結果から、これらの容易に実現可能な生活習慣は、特に高リスクで増加傾向にある高齢者集団において、心房細動の発症率を低下させ得る予防策としてさらに評価されるべきである」と述べている。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
シクロスポリンが急性心筋梗塞後の梗塞サイズを縮小
HealthDay News 7月30日
急性心筋梗塞患者において、経皮的インターベンション(PCI)直前のシクロスポリン投与は梗塞巣を縮小させるとの研究論文が、「New England Journal of Medicine」7月31日号に掲載された。
仏アルノー・ド・ビルヌーブArnaud de Villeneuve病院(モンペリエ)のChristophe Piot氏らは、ST上昇型急性心筋梗塞で来院した58人の患者を対象に、冠動脈造影後、ステント挿入前に、無作為にシクロスポリン2.5mg/kgポーラス投与群または生食投与の対照群に割りつけた小規模パイロット研究のデータを解析した。
その結果、シクロスポリン投与群では、トロポニンIではなくクレアチンキナーゼ放出の有意な低下が認められた。MRI評価を実施したサブグループでは、シクロスポリン投与群において、梗塞巣を反映する高信号領域の絶対量が有意に減少していた。
同誌の論説で、Derek J. HausenloyおよびDerek M. Yellonの両氏は、これらの知見は「ヒトにおける心筋再灌流傷害の存在を確証しており、primary PCIを受ける患者においては、ミトコンドリアの物質透過孔 (permeability-transition pore)が、この種の心筋傷害に対する心臓保護、および梗塞巣縮小の新規標的になることを示唆している。今や心筋再灌流傷害を真剣に考える時期にきた」と述べている。
本研究の共著者の一人はノバルティス社との、またTellon氏は製薬企業数社との資金的関係を申告している。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
Editorial
心筋バイオマーカー上昇が高死亡率に関連
HealthDay News 7月29日
一見健康的な高齢成人でも、心血管疾患の血漿バイオマーカー2つのうち1つでも上昇していれば、心臓性および非心臓性の死亡のリスクが高くなるとの研究論文が、「Journal of the American College of Cardiology」8月5日号に掲載された。
米カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)のLori B. Daniels氏らは、30〜79歳の地域居住成人957人を対象に、心筋トロポニンT(TnT)、N末端プロB型ナトリウム利尿ペプチド(NT-proBNP)の血漿レベルを測定した。
7〜9年後、TnT陽性(検出感度0.01ng/mL以上)の例では、全死亡および心血管疾患性死亡のリスクが有意に増大していた(両者とも調整ハザード比2.06)。NT-proBNP上昇例でも同様に全死亡と心血管疾患死亡が有意に増大していた(調整ハザード比はそれぞれ1対数単位増加につき1.85および2.51)。TnT陽性およびNT-proBNP上昇の両者が存在する人では生存率は有意に不良であった(調整ハザード比3.2)。
Daniel氏らは「一見健康的にみえてもTnT陽性、NT-proBNP上昇の認められる成人では、死亡リスクが増大している。TnT陽性およびNT-proBNP上昇の両者が存在するとリスクはさらに高まり、リスク増大は何年も持続する」と結論している。
Roche Diagnostic Inc.社が著者2人に対して、バイオマーカー測定試薬および資金提供を行っている。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
Copyright © 2008 ScoutNews, LLC. All rights reserved.
World Circulation News (WEB)
AHA、ACC、WHO、FDA、CDCの循環器領域関連のニュースヘッドラインを学会ホームページでお届けしています。
2 |
第73回学術集会プレナリーセッション・シンポジウム 演題締切りが迫っています |
第73回学術集会(大阪)のプレナリーセッション・シンポジウム演題登録締切りが迫っています。応募予定の先生は、お早めにご登録ください。
■プレナリーセッション・シンポジウム
新規登録:8月28日(木)正午 締切り
内容修正:8月29日(金)正午 締切り
今回のプレナリーセッション、シンポジウムはすべて「公募あり」となります。応募される方は、本文(タイトル、著者名、所属機関名を除く) 260 words 以内の英文抄録を登録してください。
プレナリーセッション、シンポジウム両セッションを通じて、応募できるのは一人につき1テーマのみです。
→応募要領および演題登録はこちら
3 |
循環器専門医研修施設・研修関連施設 指定および指定更新申請について |
<指定申請>
循環器専門医研修施設・研修関連施設の2009年度指定申請を受け付けています。
指定を希望する施設は、要項に従って申請手続きをしてください。
→申請はこちら
<指定更新申請>
2009年4月1日に循環器専門医研修または研修関連施設の指定更新を迎える施設に、「更新に関するご案内」を各施設の申請者にお送りしました(8/21発送)。該当する施設は指定更新の申請をお願いします。
→詳細はこちら
4 |
Circulation Journal:採択論文のオンラインジャーナル早期掲載のサービスを開始しました
|
Circulation Journalでは、現在のオンラインジャーナルに加えて、2008年8月26日より、採択論文の早期掲載のサービスをスタートしました。
採択後の著者校正が完了した論文のうち、掲載準備が完了したものから順次アップします。どうぞ、ご活用下さい。
5 |
Circulation Journal:Case Reportの取り扱いを中止します |
Circulation Journalでは、2008年10月末をもってCase Reportの受付を中止することとなりました。
既に投稿されたCase Reportはこれまで通り取り扱いますが、11月以降は新規のCase Reportの受付は認められません。
本誌の学術的レベルを高めることを目指す編集委員会の決定です。ただし、少数例による臨床論文でも学術的インパクトが高いと認められる論文は、原著論文(Clinical Investigation、またはRapid Communication)として取り扱います。
JCS Newsletterのバックナンバーをこちらのページでご覧いただけます。
ご意見・ご感想、配信先の変更・中止等は下記のアドレスまでご連絡ください
news-m@j-circ.or.jp
発行:(社)日本循環器学会 http://www.j-circ.or.jp/
本メールに記載された記事を、許可なく転載することを禁じます。
Copyright © The Japanese Circulation Society. All rights reserved.
|



