|
Vol.44 (2008.10.15)
- World Circulation News PLUS
- 第2回日本循環器学会プレスセミナー開催報告
- 第73回学術集会 コメディカルセッション
一般演題の締切が迫っています
|
|
日本人の心筋梗塞をテーマに第2回日本循環器学会プレスセミナーを開催しました。詳細は下記記事をご覧ください。
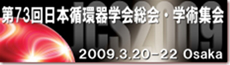
|
◆JCS2009〜第73回日本循環器学会総会・学術集会 公式ホームページはこちら◆
|
| |
|
[PR記事]
|
|
新規にご登録いただいた先生方に、
もれなく★2GB・USBメモリ★を差し上げます
|
|
|
|
Medical Tribuneの医学情報Webサービス(無料)★会員登録募集中
独自取材記事。Medical Tribune紙11年分の記事検索。
医療裁判「判例集」検索。医学専門日英辞書。
日本語でPubMed検索できます。2009年医学会カレンダー。
ご登録はこちらから → http://mtpro.jp
|
|
 |
|
|
1 |
World Circulation News PLUS(Health Day News 提供) |
海外の循環器系ニュースの短報(和訳)をお届けします。(利用規約)
薬剤溶出ステントは急性心筋梗塞後の死亡率を低減
HealthDay News 9月24日
急性心筋梗塞(AMI)に対するステント留置後2年において、薬剤溶出ステントを用いた患者ではベアメタルステントを用いた患者に比べて、死亡率および血行再建術の再施行率が有意に低いとの研究論文が、「New England Journal of Medicine」9月25日号に掲載された。
米ブリガム・アンド・ウィメンズ病院およびハーバード大学医学部(ボストン)のLaura Mauri氏らは、2003〜2004年に急性心筋梗塞の治療を受けた患者7,217人(薬剤溶出ステント例4,016人、ベアメタルステント例3,201人)の転帰を比較検討した。
1:1でマッチング(対応付け)した分析において、薬剤溶出ステント例では、2年後の調整死亡率が、全心筋梗塞患者(10.7% vs. 12.8%)、ST上昇患者(8.5% vs. 11.6%)、ST非上昇患者(12.8% vs. 15.6%)のいずれにおいても有意に低かった。また、薬剤溶出ステント例では、心筋梗塞の再発率および血行再建術の再施行率が低かった。
著者らは「我々の分析の主要目的は、心筋梗塞患者の非選択集団において、薬剤溶出ステントの有害性をメタルステントと比較検討することであった。薬剤溶出ステントによる死亡率低減が観察されたことは予想外のことであり、無作為化比較試験で確認する意義がある」と述べている。
Mauri氏は、Medtronic Vascular、Abbott Vascular、Boston Scientific、Cordisの各社との金銭関係を明らかにしている。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
MRIにより頸動脈プラーク内出血の検出が可能に
HealthDay News 9月18日
MRIは、頸動脈におけるプラーク内出血の非侵襲的評価法であり、動脈硬化性疾患のハイリスク群に属する患者の同定(特定)が可能であるとの研究論文が、「Radiology」10月号に掲載された。
カナダ、トロント大学のRichard Bitar氏らは、頸動脈内膜剥離術を受けた患者11人のデータを分析。手術前に施行したプラークのMRI画像を内膜剥離術で採取した組織切片標本とマッチングさせ、合計97個の画像と組織切片の対比を行った。
専門医の判読の結果、MRI上の高信号と組織学的に確認されたプラーク内出血との間に強い一致をみた。T1強調画像での出血検出について、2人の読影者の判定結果は、感度(sensitivity)は100%、94%、特異度(specificity)は80%、88%、陽性適中度(positive predictive value)は70%、78%、陰性適中度(negative predictive value)は100%、97%であった。
著者らは「3次元高解像画像の構築と適用範囲の拡大を組み合わせることにより、複雑化した頸動脈プラークの詳細な評価が可能となる。この非侵襲的検査は、頸動脈のハイリスク動脈硬化性疾患の縦断的研究において使用可能な評価法である」と結論している。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
好中球/リンパ球比が冠動脈疾患患者の独立した死亡予測因子に
HealthDay News 9月15日
好中球/リンパ球比(NLR)は、比較的安価な炎症マーカーであり、ハイリスク群患者の同定(特定)や急性冠症候群(ACS)患者のリスク層別化に有用であるとの研究論文が、「American Journal of Cardiology」9月15日号に掲載された。
米ミシガン大学(アナーバー)のUmesh U. Tamhane氏らは、NLRを用いて同大学病院に急性冠症候群と診断されて入院した2,833人を対象に、院内および6カ月死亡を予測した。多変量ロジスティック回帰モデルを用い、Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE)リスクプロファイルを用いて併存症の調整後、NLRと院内および6カ月死亡の関連性の評価を行った。
患者564人がST上昇型心筋梗塞、2,269人がST非上昇型急性冠症候群と診断された。NLRが最高3分位(tertile 3)に入る患者は最低3分位(tertile 1)の患者に比べて、院内死亡率(8.5% vs. 1.8%)、6カ月死亡率(11.5% vs. 2.5%)とも有意に高かった。GRACEリスクプロファイルの調整後、最高3分位の患者では院内死亡が2.04倍、6カ月死亡は3.88倍高くなっていた。
著者らは「我々の研究における最も重要な知見は、急性冠症候群患者において、NLRは院内および6カ月死亡の独立した予測因子になるということである。NLR高値の患者は、GRACEリスクプロファイルがいずれの分位においても死亡率が高まっていることから、(MLRは)急性冠症候群患者におけるリスク層別化レベルに追加されるべき項目となる」と述べている。
著者らは、本研究の実施にあたってSanofi-Aventis社の制限のない助成金の中から、部分的な援助を受けている。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
Copyright © 2008 ScoutNews, LLC. All rights reserved.
World Circulation News (WEB)
AHA、ACC、WHO、FDA、CDCの循環器領域関連のニュースヘッドラインを学会ホームページでお届けしています。
毎年9月の最終日曜日(本年は9月28日)は「世界ハートの日(World Heart Day)」です。「世界ハートの日」とは、世界心臓連合(WHF)が提唱する地球規模の心臓病啓発活動であり、この活動の一環として日本循環器学会では、9月26日(金)に報道関係者の皆様を対象にしたセミナーを開催いたしました。
今回は命に関わる病気「心筋梗塞」の現状と理解を深めていただく意味を込め、テーマを「日本人の心筋梗塞 命にかかわる病気「心筋梗塞とは」〜世界ハートの日2008〜」とさせていただきました。
座長に小川 久雄先生、講師には野々木 宏先生 、水野 杏一先生 、堀 正二先生、和泉 徹先生を迎え盛況に終了いたしましたのでご報告いたします。
| |

■座長:小川久雄先生
|
|

■セミナー風景
|
| |

■講師:野々木宏先生 |
|

■講師:水野杏一先生 |
|

■講師:堀正二先生 |
|

■講師:和泉徹先生 |
3 |
第73回学術集会 コメディカルセッション一般演題の締切が迫っています |
第73回日本循環器学会学術集会では、コメディカルの方を対象としたセッションを会期中に3日間行います。
日本循環器学会の会員でなくても演題応募、発表、参加ができますので、コメディカルスタッフの皆様方には奮ってご応募くださいますようご案内申しあげます。
なお、今大会における新たな試みとしてコメディカル一般演題においても口述発表を設けることになりましたので、口述発表とポスター発表の両方を募集します。
・コメディカルセッション 一般演題 :10月23日(木)正午 演題応募締切り
→ コメディカルセッション演題応募要領はこちら
JCS Newsletterのバックナンバーをこちらのページでご覧いただけます。
ご意見・ご感想、配信先の変更・中止等は下記のアドレスまでご連絡ください
news-m@j-circ.or.jp
発行:(社)日本循環器学会 http://www.j-circ.or.jp/
本メールに記載された記事を、許可なく転載することを禁じます。
Copyright © The Japanese Circulation Society. All rights reserved.
|



