|
Vol.45 (2008.10.28)
- World Circulation News PLUS
- 第73回学術集会(大阪)宿泊手配のご案内
- Late Breaking Clinical Trials 演題募集のご案内
- 第73回学術集会 コメディカルセッション
一般演題の締切が迫っています
|
|
第73回学術集会への参加者向けに特別料金で宿泊のご案内しております。
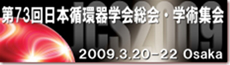
|
◆JCS2009〜第73回日本循環器学会総会・学術集会 公式ホームページはこちら◆
|
| |
[PR記事]

|
|
四大誌 完全日本語要約配信!
旬読!ジャーナル四天王
「JAMA」「NEJM」「Lancet」「BMJ」が完全日本語要約で
先生のお手元に定期的に届きます(登録・利用無料)
ご登録はこちらから (提供)ケアネット・ドットコム
|
|
|
|
| |
|
[PR記事]
|
|
新規にご登録いただいた先生方に、
もれなく★2GB・USBメモリ★を差し上げます
|
|
|
|
Medical Tribuneの医学情報Webサービス(無料)★会員登録募集中
独自取材記事。Medical Tribune紙11年分の記事検索。
医療裁判「判例集」検索。医学専門日英辞書。
日本語でPubMed検索できます。2009年医学会カレンダー。
ご登録はこちらから → http://mtpro.jp
|
|
 |
|
|
1 |
World Circulation News PLUS(Health Day News 提供) |
海外の循環器系ニュースの短報(和訳)をお届けします。(利用規約)
多くの患者で待機的PCI前の運動負荷試験が実施されていない
HealthDay News 10月14日
安定冠動脈疾患を有するメディケア利用患者を対象とした調査で、その大半において待機的経皮的冠動脈インターベンション(PCI)施行前の90日以内に、運動負荷試験が実施されていなかったとの研究論文が、JAMA「Journal of the American Medical Association」10月15日号に掲載された。
米カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)のGrace A. Lin氏らは、メディケアの有料サービス受給者で年齢65歳以上、かつ待機的PCIを受けた23,887人のデータを分析した。
権威ある組織発行のガイドラインでは、安定狭心症患者において、少なくとも中等度以上の虚血が、PCIで拡張すべき血管と関連していることが必要とされている。
PCI前90日以内において、負荷試験が実施された患者は44.5%であり、地域差が認められた。低頻度の負荷試験実施と関連する因子は、女性、年齢85歳以上、うっ血性心不全の既往歴であった。胸痛歴および黒人は、高頻度の実施と関連していた。
論説者は「著者らが述べているように、今回の知見は必ずしも(待機的PCIの)誤った利用状況を立証するものではない。この種の管理データベースには、PCI利用状況の観察されるパターンを説明かつ正当化できる多様な臨床的要因は含まれていない。しかしながら、今回の分析では、PCIへの紹介は、客観的な心筋虚血のエビデンスより、むしろ付帯的な要因によってもたらされたというはっきりした印象を与える。PCI施行前の負荷試験実施率に大きな地域差がみられることが、この結論をさらに支持する」と述べている。
Abstract
Full Text
Editorial
Heart Rate Turbulenceが急性心筋梗塞後の転帰リスクの予測因子に
HealthDay News 10月14日
Heart rate turbulence(HRT: 心拍数の乱れ)、すなわち心電図上で瞬間的な血行力学的障害が認められる変化は、心臓発作後の重篤な転帰リスクの予測因子として用いることができるとのレビューが、JACC「Journal of the American College of Cardiology」10月21号に掲載された。
ドイツ、ミュンヘン工科大学病院(ミュンヘン)のAxel Bauer氏らはHeart rate turbulenceに関し、測定法、生理学的背景と解釈、臨床応用についてレビューを行った。
Heart rate turbulenceは、期外収縮による短時間の心拍数増加に続く緩徐な心拍数低下、さらに期外収縮前への心拍数回復過程からなる。初期段階の心拍数増加は、期外収縮の結果として生じる血行力学的に不十分な心室収縮が原因となっており、圧受容体求心性刺激の消失と一過性の迷走神経刺激低下を生じ、そのことが心拍数増加につながるとのエビデンスが存在する。この後に続いて起こる心拍数低下は、交感神経刺激による動脈圧の急上昇が迷走神経刺激を来すためであると著者らは解説している。
Heart rate turbulenceは24時間ホルター心電図記録によって評価可能である。著者らはHeart rate turbulenceが圧受容体反射の間接的評価法であることを指摘した上で、急性心筋梗塞後のリスク評価と予測、さらに心不全進行のモニタリングに有用であると述べている。
Bauer氏らは「数件の大規模後向きおよび前向き研究により、Heart rate turbulenceは心筋梗塞後の最強の独立したリスク予測因子の一つであることが確認されている。Heart rate turbulenceを大規模前向き介入研究に用いるべき段階に来ている」と結論している。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
心臓再同期療法は心房細動を有する心不全患者に有益
HealthDay News 10月2日
心房細動を有する心不全患者には心臓再同期療法(cardiac resynchronization therapy)が有益であり、身体機能や左室駆出率(EF)の改善が得られるとの研究論文が、JACC「Journal of the American college of Cardiology」10月7日号に掲載された。
米ハーバード大学医学部(ボストン)のGauray A. Upadhyay氏らは、心房細動患者および正常洞調律患者において心臓再同期治療の効果を比較した5件の研究のメタ解析(対象となった患者数は合計1,164人)を行った。
その結果、両群ともに心臓再同期療法は有益であった。心房細動患者では1年後の死亡率の有意な増加はなく、また両群ともNYHA(ニューヨーク心臓協会)重症度分類における改善度は同程度であった。心房細動群に比べて洞調律群では6分間歩行試験の歩行距離およびQOL指標のミネソタスコアの改善度が大きかった。しかし、心房細動患者では、洞調律患者に比べて差は小さいものの有意な左室駆出率の増加が認められた。
Upadhyay氏らは「心房細動患者では、心臓再同期治療後に有意な改善効果が認められた。左室駆出率では洞調律患者と同等かそれ以上の改善がみられたが、機能的転帰ではその利益はより小さかった」と結論している。
本論文著者のうち数人は、医療機器企業との財務関係を報告している。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
Editorial
Copyright © 2008 ScoutNews, LLC. All rights reserved.
World Circulation News (WEB)
AHA、ACC、WHO、FDA、CDCの循環器領域関連のニュースヘッドラインを学会ホームページでお届けしています。
2009年3月20日(金・祝)〜 22日(日)に開催される第73回学術集会への参加者向けに、特別料金で宿泊のご案内を申し上げます。
なお部屋数には限りがありますので、ご希望の宿が満室の場合には何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
→ 宿泊のお申し込みは、学術集会公式ホームページの「宿泊案内」コーナーから。
3 |
Late Breaking Clinical Trials 演題募集のご案内 |
第73回日本循環器学会総会・学術集会では、セッション「Late Breaking Clinical Trials」(公募・一部指定)を開催いたします。
応募内容は、本学会で初めて結果を公表されるもので、かつ他の学会に発表または応募をされていない Clinical Trials を最優先いたします。
ただし既に発表されたものであっても、本学会で改めて発表を希望されるTrialにつきましても採用を考慮いたしますので、奮ってご応募下さい。
演題募集締切:2008年11月21日(金)正午 必着
→ Late Breaking Clinical Trials 演題応募要領はこちら
4 |
第73回学術集会 コメディカルセッション一般演題の締切が迫っています |
第73回日本循環器学会学術集会では、コメディカルの方を対象としたセッションを会期中に3日間行います。
日本循環器学会の会員でなくても演題応募、発表、参加ができますので、コメディカルスタッフの皆様方には奮ってご応募くださいますようご案内申しあげます。
なお、今大会における新たな試みとしてコメディカル一般演題においても口述発表を設けることになりましたので、口述発表とポスター発表の両方を募集します。
・コメディカルセッション 一般演題 : |
10月23日(木)正午 演題応募締切り |
| |
10月30日(木)正午 演題応募締切り |
→ コメディカルセッション演題応募要領はこちら
JCS Newsletterのバックナンバーをこちらのページでご覧いただけます。
ご意見・ご感想、配信先の変更・中止等は下記のアドレスまでご連絡ください
news-m@j-circ.or.jp
発行:(社)日本循環器学会 http://www.j-circ.or.jp/
本メールに記載された記事を、許可なく転載することを禁じます。
Copyright © The Japanese Circulation Society. All rights reserved.
|



