|
Vol.53 (2009.3.10)
- World Circulation News PLUS
- 第20回循環器専門医資格認定試験 受験申請書類受付中です
|
|
第20回 循環器専門医資格認定試験 受験申請書類請求期間は3月3日〜3月23日までとなります。
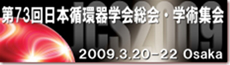
|
◆JCS2009〜第73回日本循環器学会総会・学術集会 公式ホームページはこちら◆
◆APCC2009〜第17回アジア太平洋心臓病学会 公式ホームページはこちら◆
|
| |
[PR記事]

|
|
四大誌 完全日本語要約配信!
旬読!ジャーナル四天王
「JAMA」「NEJM」「Lancet」「BMJ」が完全日本語要約で
先生のお手元に定期的に届きます(登録・利用無料)
プレゼントキャンペーン実施中こちらから
(提供)ケアネット・ドットコム
|
|
|
1 |
World Circulation News PLUS(Health Day News 提供) |
海外の循環器系ニュースの短報(和訳)をお届けします。(利用規約)
怒りがICD患者の再分極不安定性と不整脈を誘発
HealthDay News 2月24日
再分極不安定性のマーカーとなる怒り誘発性のT波交代現象(anger-induced T-wave alternans: TWA)が、埋め込み型除細動器(ICD)患者における心室性不整脈の予測因子となり、ストレスと突然死の関連性を示す情報を提供するとの研究論文が、「Journal of the American College of Cardiology」3月3日号に掲載された。
米エール大学医学部(コネティカット州ニューヘブン)のRachel Lampert氏らは、精神的ストレスプロトコル施行中に誘発されるTWAが心室性不整脈を予測しうるかどうかを、ICD患者62人を対象に検討した。
最短1年以上の追跡期間中、ICD作動による不整脈停止(ICD-terminated arrhythmias)を認めた患者10人では怒り誘発性TWAが有意に高かった(13.2マイクロボルト[μV] vs. 9.3 μV)。延長追跡期間では、怒り誘発性TWAが最高4分位の患者群(11.9 μVより大)で不整脈発生率がより高かった(40% vs. 9%)。交絡因子の調整後において、怒り誘発性TWAはICD作動による不整脈停止の独立した予測因子であり、最高4分位患者群では不整脈発生リスクは10.8倍高かった。
米ストーニィブルック大学医療センター(ニューヨーク州ストーニィブルック)のEric J. Rashba氏は論説において、「誘発試験中に高度の怒り誘発性TWAを認める患者は、追跡期間中にICDで検知される心室性不整脈のリスクがより大きいことを示した最初のエビデンスである」と述べている。
PinMed社が、本研究で使用された再分極解析ソフトウェアを提供し、研究著者のうち2人は同社社員であり、1人は一定以上のオーナーシップ株所有者である。本研究論文および論説の著者らはデバイス企業との関係を申告している。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
Editorial
3枝、左主幹部冠動脈病変にはCABGが最善
HealthDay News 2月18日
3枝または左主幹部冠動脈疾患患者においては、冠動脈インターベンション(PCI)ではなく、冠動脈バイパス手術(CABG)のほうが心血管および脳血管イベントの発生率が低いことから、CABGを標準的治療法として存続させるべきであるとの研究論文が、「New England Journal of Medicine」オンライン版に2月18日掲載された(印刷版は3月5日号掲載予定)。
オランダ、エラスムス大学医療センター(ロッテルダム)のPatrick W. Serruys氏らは、3枝病変または左主幹部冠動脈病変を有しCABGまたはPCIを受けた患者1,800人を対象とした無作為化研究を実施した。患者には治療介入後12カ月間の追跡が行われた。
研究期間中、PCI施行患者ではCABG施行患者に比し、主要心血管または脳血管イベントの発生率が有意に高かった(17.8% vs. 12.4%)。これは再血行再建術を受けた患者の比率増大に起因するところが大きかった(PCI群13.5% vs. CABG群5.9%)。死亡率では2群間に有意差は認めなかったが、CABG患者では脳卒中の発生率がより高かった。
著者らは「我々の研究結果は、3枝あるいは左主幹部冠動脈疾患、または両者を有する患者では、CABG施行による1年後の主要心血管および脳血管の有害事象の発生率はPCIに比べて低いことを示しており、このような患者に対しては、CABGを標準的治療法として存続させるべきである」と結論している。
本研究はボストン・サイエンティフィック社の支援を受けており、研究著者の数人は製薬企業との財務関係を明らかにしている。
Abstract
Full Text
メタボリックシンドロームは血圧の食塩感受性を増大させる
HealthDay News 2月16日
メタボリックシンドロームは血圧の食塩感受性と有意に関連しているとの研究論文が、「Lancet 」2月16日号オンライン版に掲載された。
米チュレーン大学医学部(ニューオーリンズ)のJing Chen氏らは、16歳以上の中国系非糖尿病者1,906人を対象に研究を実施。被験者らは、7日間の減塩食摂取後、7日間の高食塩食を摂取した。メタボリックシンドロームに関する情報が得られた対象者1,881人のうち、283人がメタボリックシンドロームであった。
減塩食および高食塩食摂取の双方において、メタボリックシンドロームを有する被験者では血圧の多変量調整平均変化(multivariable-adjusted mean changes)が有意に大きかった。メタボリックシンドロームの危険因子(リスクファクター)をもたない被験者に比し、4〜5個の危険因子を有する被験者では、減塩食および高食塩食摂取期間中の食塩感受性が有意に高かった(オッズ比3.54および3.13)。
著者らは「これらの結果は、メタボリックシンドロームにより食塩摂取に対する血圧の反応性が増強されることを示唆している。メタボリックシンドロームの複合危険因子をもつ患者では、減塩が血圧降下を図る上で特に重要な要素となる」と結論している。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
Copyright © 2008 ScoutNews, LLC. All rights reserved.
World Circulation News (WEB)
AHA、ACC、WHO、FDA、CDCの循環器領域関連のニュースヘッドラインを学会ホームページでお届けしています。
2
|
第20回循環器専門医資格認定試験 受験申請書類受付中です
|
第20回(2009年度)循環器専門医資格認定試験 受験申請書類請求を受付中です。
請求期間は3月3日(火)10時〜3月23日(月)17時までです。請求期間後は一切受付できませんのでご注意
ください。
→ご請求はこちら
JCS Newsletterのバックナンバーをこちらのページでご覧いただけます。
ご意見・ご感想、配信先の変更・中止等は下記のアドレスまでご連絡ください
news-m@j-circ.or.jp
発行:(社)日本循環器学会 http://www.j-circ.or.jp/
本メールに記載された記事を、許可なく転載することを禁じます。
Copyright © The Japanese Circulation Society. All rights reserved.
|



