|
Vol.54 (2009.3.31)
- World Circulation News PLUS
- Translational Research振興事業
- 学会誌Circulation Journal送本不要申告手続き
|
|
3月31日までに受付けた申告書につきましては4月20日発行のVol.73 No.5より送本を停止します。
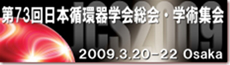
|
◆JCS2009〜第73回日本循環器学会総会・学術集会 公式ホームページはこちら◆
◆APCC2009〜第17回アジア太平洋心臓病学会 公式ホームページはこちら◆
|
| |
|
|
|
| |
 |
|
Registry STATIONは、全国の医師が処方経験を共有、閲覧できるシステムです。多様な背景を有する臨床「現場」に即したデータが集積され、入力した患者さんのデータを全国と比較することも可能です。
ローコールRegistry STATIONは、スタチンで初めてのRegistry STATIONで、アドヒアランスと治療効果の関係を明らかにすることも目的にしています。是非ご参加ください。
|
|
|
1 |
World Circulation News PLUS(Health Day News 提供) |
海外の循環器系ニュースの短報(和訳)をお届けします。(利用規約)
吸収性everolimus溶出ステントは安全かつ有効
HealthDay News 3月13日
臨床試験において、生体吸収性everolimus(エベロリムス)溶出性冠動脈ステントシステムは臨床的に安全であり、血管運動性を回復、再狭窄を防止するとの試験結果が、「Lancet」3月14日号に掲載された。
オランダ、エラスムス医療センター(ロッテルダム)のPatrick W. Serruys氏らは、患者30人を対象に生体吸収性everolimus溶出冠動脈ステントシステムを用いて冠動脈一枝病変を治療し、複数の画像診断により2年間追跡した研究を行った。
患者29人について2年間のデータが得られたが、本デバイスは安全で、心臓死はなく、心筋梗塞は1例のみであった。ステントから溶出した薬剤に反応し血管運動性がステント留置部位および近傍冠動脈に認められた。血管径の変化はみられなかったがプラークが縮小したことにより、血管内腔断面積の増加が認められた。
著者らは「異物の消失と血管運動性の回復は、晩期(late)血栓症の危険性を伴わない正常な治癒血管維持への希望が持たれる。大規模研究において、これらの知見を確認する必要があるが、本デバイスまたは類似デバイスは、血流制限を伴うプラークの治療において、血管の健全性回復のために非常に重要となる」と述べている。
本研究は、生体吸収性everolimus冠動脈ステントシステムを製造している米Abbott Vascular社の後援を受けており、一部の共著者はAbbott社の従業員や諮問委員になっている。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
非急性冠動脈疾患のファーストステップには依然として薬物療法が最善
HealthDay News 3月13日
非急性冠動脈疾患に対しては、カテーテル治療における技術的革新が認められるものの、薬物療法が依然として最善の初期治療戦略であるとの研究論文が、「Lancet」3月14日号に掲載された。また同号では、経皮的冠動脈インターベンション(PCI)時に血小板プロテアーゼ活性化受容体-1の経口拮抗薬であるSCH 530348を用いた第II相試験のポジティブな初期知見が報告された。
米タフツ医療センター(ボストン)のThomas A. Trikalinos氏らは、非急性冠動脈疾患に対する4つの介入法を比較した、患者総数25,388人を対象に含む61件の研究のメタアナリシスを行った。介入法は、経皮的バルーン冠動脈形成術、ベアメタルステント、薬剤溶出性ステント、薬物療法の4種類。その結果、薬物療法との比較で、各種カテーテル療法において死亡率および心筋梗塞発生率を改善させるエビデンスは得られなかった。
一方、米デューク臨床医学研究所(ノースカロライナ州ダーラム)のRichard C. Becker氏らは、非緊急でPCIを施行、または冠動脈造影時に予定(planned )PCIを施行した患者総数1,030人を対象とした研究を行った。対象患者のうち773人はSCH 530348を10mg、20mg、40mgのいずれかの用量で投与され、257人はプラセボを投与された。その結果、本薬剤の忍容性は良好であり、心筋梗塞部(TIMI)出血における血栓溶解を増加させることはなかった。
Becker氏らは「我々の研究は、PCIを受けた冠動脈疾患患者におけるトロンビン受容体阻害の妥当性と安全性の予備的エビテンスを示している。安全性および有効性についてより詳細な情報を得るには第III相試験が必要である」と述べている。
後者の研究は、Schering-Plough Research Institute(ニュージャージー州ケニルワース)の資金提供を受けており、数人の共著者にはSchering-Plough Research Instituteから資金提供や謝礼支払いがされている。
Abstract - Trikalinos
Full Text (subscription or payment may be required)
Abstract - Becker
Full Text (subscription or payment may be required)
高齢心不全患者では薬物療法による生存率向上効果なし
HealthDay News 3月12日
心不全を有する80歳以上の高齢者で左室駆出率(LVEF)が保たれている患者がよくみられるが、このような患者に対し、一般的に処方されている循環器薬による顕著な有益性は認められないとの研究論文が、「American Journal of Cardiology」3月15日号に掲載された。
米シダーズサイナイ医療センター(ロサンゼルス)のFaramarz Teheani氏らは、心不全を有していながらもLVEFが保たれている平均年齢87歳の患者142人について検討を行った。患者の使用薬剤としては、スタチン、ACE阻害薬、アンジオテンシンII受容体拮抗薬、β遮断薬、利尿薬、Ca拮抗薬、硝酸薬、ジゴキシンが含まれていた。本コホートは5年間追跡され、その間、98人(69%)が死亡した。
5年時点では、死亡患者と生存患者との間で追跡開始時パラメータに有意差はなかった。調整全死亡率または心疾患による再入院率については、いずれの薬物にも有意の低下効果はなく、また長期生存率にも有意差はなかった。
著者らは「高齢者では、多剤併用および薬物動態変化のために薬剤による副作用リスクは高く、慎重な薬物使用をすべきである。80歳以上でLVEFが保たれている心不全患者では、薬物療法について明らかな有益性は示されていない」と述べている。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
Copyright © 2008 ScoutNews, LLC. All rights reserved.
World Circulation News (WEB)
AHA、ACC、WHO、FDA、CDCの循環器領域関連のニュースヘッドラインを学会ホームページでお届けしています。
2
|
Translational Research振興事業
|
日本循環器学会学術委員会では、数多くの診療ガイドライン策定や臨床研究推進に取り組んでおりますが、2009年度よりこの活動をさらに発展させ、最近の再生医学の進歩も含めて、臨床応用に後一歩の所迄来ている最先端の基礎的研究あるいはtranslational researchを日本循環器学会として支援し、海外に先駆けてデータを発信して行きたいと存じます。国の施策として最先端の再生医療、医薬品開発等を念頭に置いた「先端医療開発スーパー特区」構想も出されており、公的資金導入のための支援策にもなるような、先端医療研究拠点設置等も学会主導で進められればと考えております。
本振興事業は、学会としての研究支援事業の一環として位置づけられるものでもあります。応募については下記をご確認ください。
「Translational Research振興事業」
3
|
学会誌Circulation Journal送本不要申告手続き
|
3月31日までに受付けた申告書につきましては4月20日発行のVol. 73 No. 5より送本を停止します。今後も随時申告を受付けます。詳細はHPにてご確認願います。
JCS Newsletterのバックナンバーをこちらのページでご覧いただけます。
ご意見・ご感想、配信先の変更・中止等は下記のアドレスまでご連絡ください
news-m@j-circ.or.jp
発行:(社)日本循環器学会 http://www.j-circ.or.jp/
本メールに記載された記事を、許可なく転載することを禁じます。
Copyright © The Japanese Circulation Society. All rights reserved.
|



