|
Vol.49 (2008.12.24)
- World Circulation News PLUS
- 第73回学術集会 一般演題の採択演題をお知らせしています
- ガイドライン発刊のご案内
- AED検討委員会より情報提供のお願い
- The West Coast Cardiovascular Forumのご案内
|
|
学術集会公式ホームページにて、一般演題の採択演題をお知らせしています。
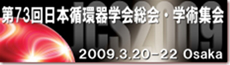
|
◆JCS2009〜第73回日本循環器学会総会・学術集会 公式ホームページはこちら◆
|
| |
[PR記事]

|
|
四大誌 完全日本語要約配信!
旬読!ジャーナル四天王
「JAMA」「NEJM」「Lancet」「BMJ」が完全日本語要約で
先生のお手元に定期的に届きます(登録・利用無料)
ご登録はこちらから (提供)ケアネット・ドットコム
|
|
|
|
| |
| [PR記事] |
|
新規にご登録いただいた先生方に、
もれなく★2GB・USBメモリ★を差し上げます
|
|
|
|
Medical Tribuneの医学情報Webサービス(無料)★会員登録募集中
独自取材記事。Medical Tribune紙11年分の記事検索。
医療裁判「判例集」検索。医学専門日英辞書。
日本語でPubMed検索できます。2009年医学会カレンダー。
ご登録はこちらから → http://mtpro.jp
|
|
 |
|
|
1 |
World Circulation News PLUS(Health Day News 提供) |
海外の循環器系ニュースの短報(和訳)をお届けします。(利用規約)
降圧薬の併用で心血管イベントリスクが低下
HealthDay News 12月3日
ACE阻害薬ベナゼプリルとCa拮抗薬アムロジピンの併用療法は、ベナゼプリルと利尿薬ヒドロクロロチアジドの併用療法よりも、心血管イベント予防の面で優れているとの研究論文が、「New England Journal of Medicine」12月4日号に掲載された。
米ミシガン大学ヘルスシステム(アナーバー)のKenneth Jamerson氏らは、ハイリスクの心血管イベントが見込まれる高血圧患者11,506人を対象とした研究を行った。患者は無作為にベナゼプリル+アムロジピン併用またはベナゼプリル+ヒドロクロロチアジド併用投与群に割り付けられた。主要評価項目は、心血管関連死亡、非致死的心筋梗塞、非致死的脳卒中、狭心症による入院、突発性心停止に続く蘇生、冠動脈血行再建治療を含む心血管イベントの複合とした。
その結果、ベナゼプリル+ヒドロクロロチアジド併用群ではベナゼプリル+アムロジピン併用群に比べ、より多くの血管イベントが生じていた(11.8%vs.9.6%)。ベナゼプリルとアムロジピン併用により、19.6%の心血管イベントの相対危険度低下がみられた。また、ベナゼプリルとアムロジピン併用は、心血管関連死亡、心筋梗塞、脳卒中リスクの有意な低下と関連していた(ハザード比0.79)。
著者らは「我々の研究では、ベナゼプリルとアムロジピンの併用療法で優れた血圧コントロールが得られただけでなく、心血管転帰の観点でも明確な有益性が認められた。今回の知見は、高血圧患者での心血管イベントリスク低減のための併用療法の選択肢が増えることを示している」と結論している。
本研究はノバルティス社の支援を受けている。論文および論説の著者らは製薬企業との財務関係を明らかにしている。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
Editorial
迅速対応チームは院内全体の心肺停止率を低下させず
HealthDay News 12月2日
迅速対応チーム(rapid response team, RRT)の導入により、集中治療施設外での心肺停止発生率の低減をもたらす可能性はあるが、院内全体での死亡率および心肺停止率(code rate)は不変のままであるとの研究論文が、「Journal of the American Medical Association」12月3日号に掲載された。
米ミズーリ大学(カンザスシティー)のPaul S. Chan氏らは、RRT導入以前の入院患者24,193人のデータと、導入後の入院患者24,978人のデータを比較した。
導入後、RRTには376回の発動があり、20カ月以内に病院全体での平均code rateは入院1000件当たり11.2件から7.5件に低下した。しかし、導入前の傾向(trend)調整後では、RRT導入により平均院内code rate、もしくは院内全体での死亡率は減少していなかった。
著者らは「RRT導入後の確固たる転帰データが欠如していることから、RRTを広く普及させる以前に、十分な長期フォローアップ期間を伴い、統計学的にも十分な患者標本数を有した良好なデザインの多施設研究により、その有効性を厳格に評価すべきである」と述べている。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
非侵襲的CT血管造影は冠動脈疾患に対しても高精度だが、従来の血管造影には及ばず
HealthDay News 11月26日
普及型CTの4倍のスキャナー性能を有する非侵襲的CT検査は、冠動脈疾患の存在診断および重症度評価において高い精度を有するが、従来の血管造影検査の精度には及ばないとの研究論文が、「New England Journal of Medicine」11月27日号に掲載された。
米ジョーンズ・ホプキンス大学医学部(ボルティモア)のJulie M. Miller氏らは、64列、0.5mmスライス厚のマルチ検出器型装置を用いたCT冠動脈造影と従来法による冠動脈造影による精度を、冠動脈疾患が疑われる患者291人(40歳以上、カルシウムスコア600以下)において比較検討した。
その結果、56%の患者は、狭窄度50%以上の定義による閉塞性冠動脈疾患を有していた。CT血管造影検査では、ROC曲線下面積(AUC)0.93、感度85%、特異度90%、陽性的中率91%であり、陰性的中率は83%であった。CT血管造影と従来法の血管造影は、引き続き血行再建術(血管再疎通治療)を要する患者の同定能において同様であった(AUC 0.84 vs. 0.82)。CT血管造影を受けた患者の2人に造影剤に対する重篤な副作用がみられた。
Miller氏らは「マルチ検出器CT血管造影は、症候性患者において閉塞性冠動脈疾患の存在診断と重症度評価、さらに継続的血行再建術を要する患者の正確な同定が可能であった。ただし、陰性および陽性的中率で判断すると、マルチ検出器CT血管造影は、現時点では従来型の冠動脈造影にとって代わるものではない」と結論している。
本研究は一部、東芝メディカルシステムズ社の資金援助を受けている。著者の数人は、製薬企業と医療機器企業との財務関係を明らかにしている。
Abstract
Full Text (subscription or payment may be required)
Editorial
Copyright © 2008 ScoutNews, LLC. All rights reserved.
World Circulation News (WEB)
AHA、ACC、WHO、FDA、CDCの循環器領域関連のニュースヘッドラインを学会ホームページでお届けしています。
2
|
第73回学術集会一般演題の採択演題をお知らせしています
|
学術集会公式ホームページにて、一般演題の採択演題をお知らせしています。採択された演題の登録番号・採択演題名・筆頭演者名をカテゴリー別に掲載していますので、ご確認ください。
→一般演題 採択演題のお知らせはこちら
循環器病の診断と治療に関するガイドライン(2006-2007年度合同研究班報告)を12月25日(木)に会員の皆様に発送いたします。
AED検討委員会(委員長:三田村秀雄)では、AEDを使用した際に、その診断に疑問を感じた経験をお持ちの先生方から、内容を(可能ならば心電図もあわせて)学会事務局あてに情報提供していただき、分析検討を行いたいと考えています。
会員各位のご協力をお願い申し上げます。
→詳しくはこちら
ご連絡先 AED検討委員会係
Email: itc@j-circ.or.jp
5
|
The West Coast Cardiovascular Forumのご案内
|
2009年6月19日〜21日にかけてアメリカのサンフランシスコで、The West Coast Cardiovascular Forumが開催されます。
詳細は、こちらをご確認ください。
JCS Newsletterのバックナンバーをこちらのページでご覧いただけます。
ご意見・ご感想、配信先の変更・中止等は下記のアドレスまでご連絡ください
news-m@j-circ.or.jp
発行:(社)日本循環器学会 http://www.j-circ.or.jp/
本メールに記載された記事を、許可なく転載することを禁じます。
Copyright © The Japanese Circulation Society. All rights reserved.
|



